07/27
2025年7月の見たり読んだり
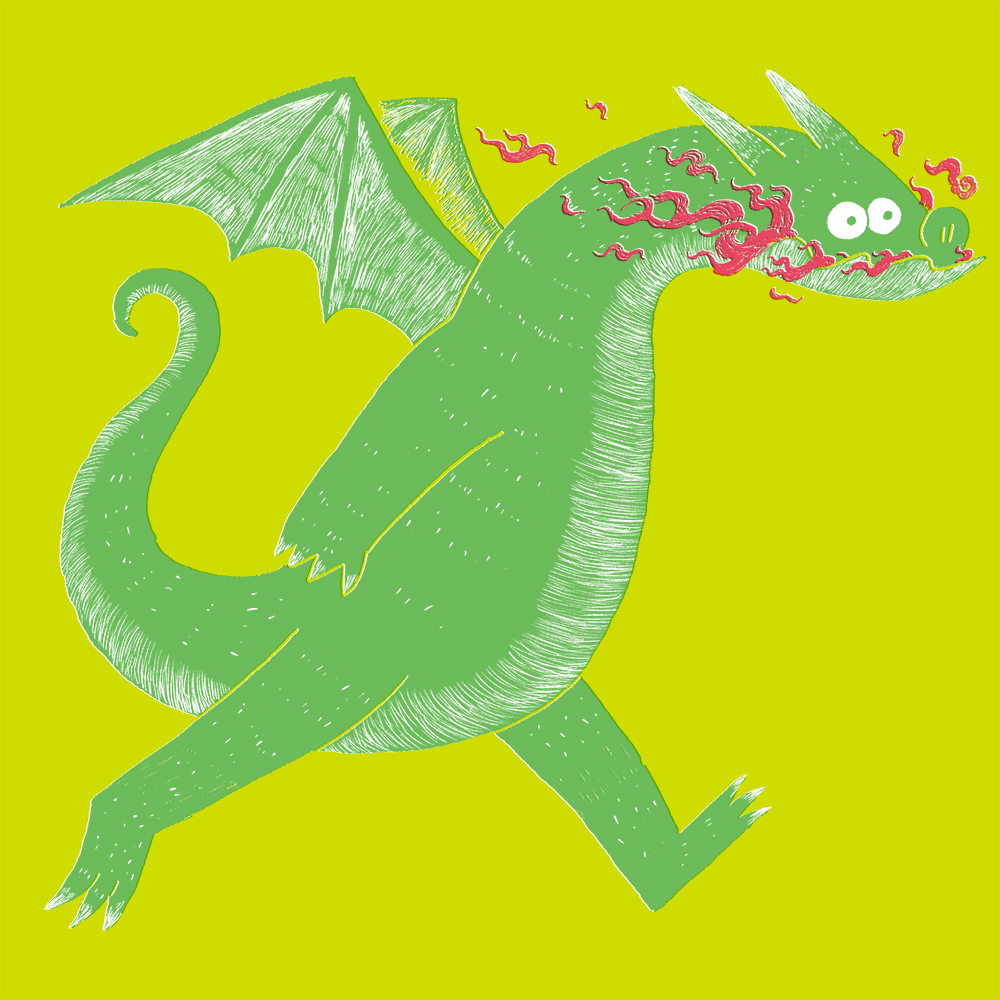
◯甲骨文字小字典/落合 淳思
今アツいといえば、甲骨文字である。漢字のルーツとされる文字だが、線に整えられる前のソレはやけに生々しく、標識でもみているような気分になって楽しいのだ。で「字通」という辞書を買う。しかし中には「ホント?」と首をひねる説明もあり、他の本をハシゴすること。この本を読んで、やっとわかった。加藤常賢さんも白川静さんも、もちろんこの本の著者さんも、甲骨文字が何をモチーフにしたのかはわからないのだ。その事実が確認できただけで読む価値があった。
◯スマホ時代の哲学/谷川 嘉浩
stayfreeというアプリがある。スマホを使った時間を計測したり、アプリの使用を制限したりしてくれる優れものだ。stayfreeを使い初めて1ヶ月した頃に、スマホの平均使用時間を測ってみた。結果は1日に40分。月で20時間をスマホに充てている計算だ。「忙しいから自分の描きたい絵に使う時間がない」と悩んでいたりしたが、時間はちゃんとあった。しかし、1日40分を全てお絵描きに使えるかというと、そうではない。もうスマホがないとダメ、、、というのが私たちだ。そこでこの本。スマホを得たことで失ったものを明らかにしつつ、できることを模索する助けとなってくれる。どうやらスマホとの付き合い方は、生きることにも関わる大事なことのようだ。
◯「朱子語類」訳注
朱子の死後、彼とお弟子さんが交わした会話を集めた「朱子語類」。全部で140巻ある。江戸幕府との繋がりのせいか、朱子には”お堅い”イメージがある。けれど弟子とのおしゃべりを読む限り、なかなか面白い人だ。きびしい人ではあったとは思うけれど・・・。
●巻一・二・三
陰陽五行説を軸に、世界を理解しようとする姿勢がアリストテレス的でステキ。「この世界を知りたい」というピュアな欲がビンビンと伝わってくる。宋代の人たちがどういう風に世界を眺めていたかを知りたい人には面白い本。
●巻七・巻十二・巻十三
私たちの知る”敬(うやま)う”とは違う、儒教の”敬”について取り上げている巻十二の特守編。この巻だけでも読む価値あり!
◯日本美術の鉱脈展/大阪中之島美術館
会場を歩くうちに「奇想の系譜」の系譜であると了解。それもそのはずで監修は「奇想の系譜」を書いた辻惟雄さんの弟子・山下裕二さんだった。並ぶのは縄文時代から現代までの狂気を帯びた作品。「エェなぁ」とニヤけながら会場をフラフラ。一番心を奪われたのが「築島物語絵巻」だった。”洗練された文字”と”模写したくなるヘタな絵”が気持ち良く交わっていて大興奮。「図録が欲しい!」と、会場の売店を探すもない。ネットを探すと図録はあったものの、手に入らない。出版元に問い合わせても、在庫はもうないとのことだった。あぁ、欲しい。



